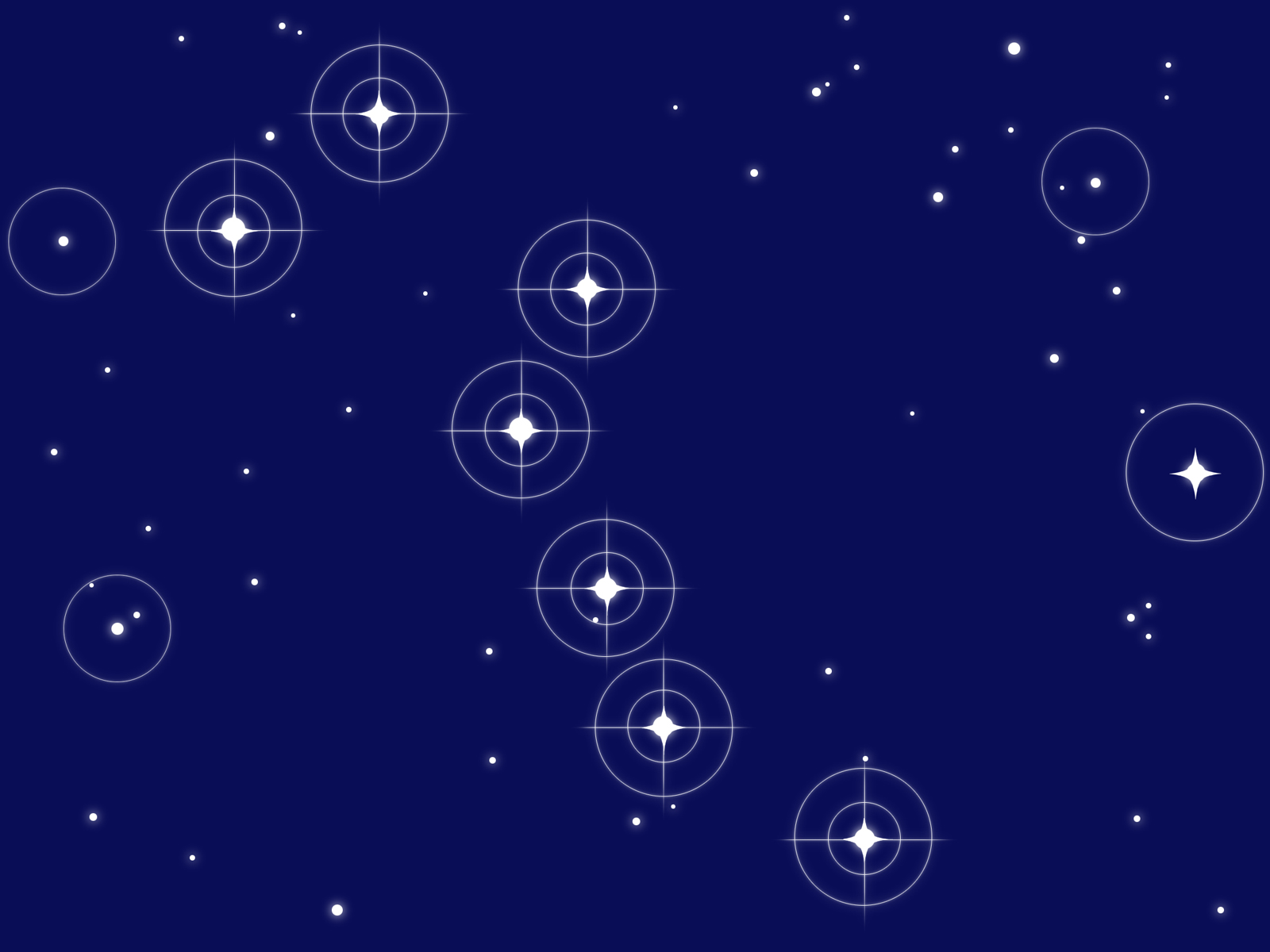「六曜」とはカレンダーなどでも見かける「大安(たいあん・だいあん)」や「仏滅(ぶつめつ)」などを含めたその日の吉凶などいわゆる「お日柄(ひがら)」を示すもののことで、暦には「歴注(れきちゅう)」として掲載されているものです。
「六曜」には良く知られている「大安」「仏滅」の他に「友引(ともびき)」「先負(せんぷ・さきまけ)」「先勝(せんしょう・さきがち)」「赤口(しゃっこう・しゃっく)」があり「六輝(ろっき)」とも言われ、結婚式や葬儀などの行事を行う日取りの参考にされています。
同じ「歴注」の一つである「十二直」はその名の通り十二の日柄に分けられています。
江戸時代の暦の「歴注」の中段に載っていたので「中段」と呼ばれることもあり、昭和初期頃になって「六曜」が広まり始めるまでは、今の「六曜」以上に日常生活の中に深くとけ込み使われていたと言われています。
「十二直」のなりたち
古代中国で生まれ日本に伝えられた「十二直」は、正倉院にある天平十八年(西暦746年)の暦である「具注歴(ぐちゅうれき)」の中にも見られ、古く飛鳥時代から暦に取り入れられていたようです。
古来、中国では夜空の北斗七星の柄杓(ひしゃく)の柄(え)にあたる3つの星が指す方角で、季節や時刻を測り定める基準としていました。
その理由は北斗七星は天の北極を回る周極星で構成されているので、一年を通して一晩中天空から地平線の下へと沈むことがなかったからです。
そして神々の星であるとされる北斗七星の柄が指し示す方角に十二支をあてはめ吉凶を占っていたところより「十二直」が生まれました。
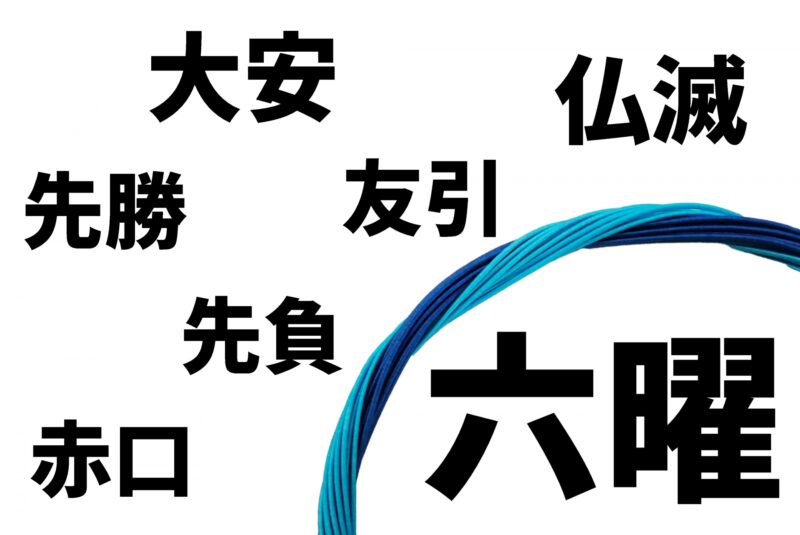
現代における「十二直」
十二種類の吉凶を判断する日柄が「建・除・満・平・定・執・破・危・成・納・開・閉」と漢字一文字で示されている「十二直」。
その「十二直」の「直」には「当たる」という意味があり、「歴注」の中でも特に当たるものとして気に留められていました。
現代のカレンダーでは「六曜」が一般的となり、「十二直」は全盛期ほどには使われなくなり知らない人も増えましたが、年配の方などは「六曜」より「十二直」の方を優先されることもあり、建築業者などの縁起を大事にする業界では今でも考慮されることが少なくありません。

「十二直」のそれぞれのお日柄
それでは十二日周期で順番に繰り返す「十二直」それぞれの日柄を、その順序通りに説明してまいります。
「建(けん・たつ)」
その字の如く、全てのものを建て生じる日とされています。
何かを起こすこと全てが吉とされ、物事を決める日や祝い事にも良い日とされています。
特に「建」ゆえに建築業界では最良の吉日とされていますが、土を動かす土木工事、植木の植え替えなどは凶とみなされています。

吉な行い:地鎮祭、棟上げ(むねあげ)、開店開業、事を始める、結婚式、会社の登記。
凶な行い:土木工事、蔵開き(新年を迎えて初めて蔵を開く事)、船に乗り始めること。
「除(じょ・のぞく)」
不浄なものや障害など悪いことを取り除くとされている日ですが、「建」同様に土を動かすことは良くない日でもあります。

吉な行い:種まき、掃除、治療、医療、神事。
凶な行い:土木工事、婚礼、旅行。
「満(まん・みつ)」
古代中国で天上に住まう最高神を指す名前である「天帝」の蔵に宝が満ち、地上にも万物が満ち溢れる日とされている吉日。
大吉なる日であっても節度を忘れず羽目を外さぬように過ごすことが大事とされています。

吉な行い:移転や旅行、婚礼、開店、会社登記。
凶な行い:服薬の開始、土木工事。
「平(へい・たいら)」
天上の神々が人間の善悪に関わらず、万物を平等に分け与える日との意味があります。
すべて物事が平らかになる日とのことから道路の修理などにも吉とされ、反対に穴を掘る事に繋がる事は凶とされています。

吉な行い:すべてに吉、婚礼には大吉。
凶な行い:穴や溝を掘る事、種まき。
「定(てい・さだん)」
善悪を含め万事すべての物事が定まる日。
移動など「変化」につながる事は凶とされています。
吉な行い:建築、棟上げ、柱立て、種まき、開店・開業、移転、売買、結納、定まるとの事から特に婚礼には大吉。

凶な行い:訴訟や旅行、植木の植え替え。
「執(しつ・とる)」
執り行うとの意ですが、万物が育ち活動するその執行を促す日です。

吉な行い:神仏を祀る、建築、造作(ぞうさく:建物内部の仕上げ工事など)、種まき、婚礼。
凶な行い:旅行や金銭の出入りに関わる事。
「破(は・やぶる)」
破れるとの言葉から契約ごとや祝い事には凶とされていますが、一方打ち破るという突破の意味もある事から勝負事には吉。

吉な行い:訴訟、裁判、出陣。
凶な行い:契約や交渉、相談。特に婚礼には大凶。
「危(き・あやぶ・あやう)」
危険が伴う大凶の日であり基本的に何につけても自重すべき日とされていますが、祝い事や神の祭礼には吉とされています。
幸せの氣や御神気が凶を吹き飛ばすと考えられたのかも知れませんね。

吉な行い:祝い事や祭礼。
凶な行い:乗船、旅行、高所や水辺など危険を伴う場所、登山、新事業、契約や交渉、相談など。
「成(せい・なる)」
何事も成就しやすい大吉の日。
願い思っていることが成就するという、何かを始めるのに最適な日と言えます。

吉な行い:土木工事、建築、柱立て、新規事業開始、開店、種まき、婚礼。特に結納は大吉。
凶な行い:訴訟事。
「納(おさん)」
作物の刈り入れを含む、万物を取り納めるのに適した日とされています。
「天倉(てんそう)」とも呼ばれ、蔵に宝をしまう日とも言われます。

吉な行い:穀物の収穫、買い物、新築。
凶な行い:見合い・結納・婚礼、葬儀。
「開(かい・ひらく)」
神の使い、眷属が艱難を開いてくださるという日。
簡単に言えば運が開ける日であり、道が開ける日とも言えます。
特に自身の願う事、成したい事を行うのに吉です。
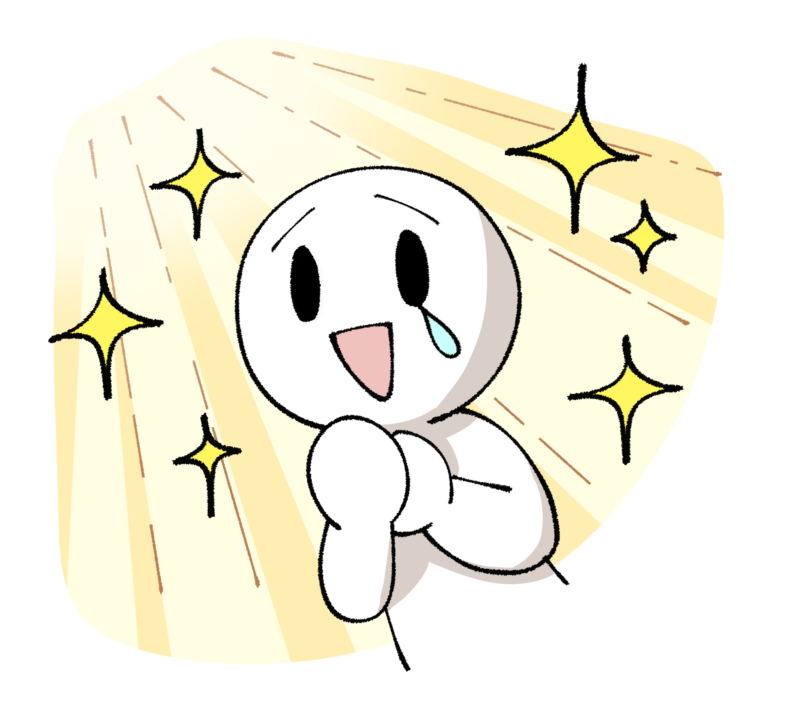
吉な行い:地鎮祭、棟上げなど建築関連、入学、学びごと、種まき、開業、造作、婚礼、引越し、出張など。
凶な行い:葬式や不浄とされる事。
「閉(へい・とづ・とず)」
全てが閉ざされ、閉じ込められるというと、万事に悪い日という印象ですが、閉ざしてしまいたい、繰り返したくないことなどには良い日でもあります。

吉な行い:葬儀、墓づくり、池の埋め立て、家屋の穴を塞ぐ修理。
凶な行い:地鎮祭、棟上げなど建築関連、旅行、婚礼、開業。

まとめ
昭和初期までの暮らしの中には深く入り込んでいた「十二直」ですが、インターネットの普及により専門的な情報も手に入りやすくなった事からか、また近年注目されてきています。
とは言えあまりとらわれ過ぎるのではなく、ここ一番といった時に良い縁起を担いで気持ちをよりポジティブにしたり、建築や祝い事などの行事を皆でより気持ちよく分かち合う為に「十二直」を参考にしていただければ幸いです。